 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
エッセイみたいな長文YOUTUBEでは珍しいね。
数ヶ月前、品川図書館からおよそ30枚ほど、世界の民族音楽のCDを借りて、PCに保存しておいた。それを「東南アジア」とか「中東」とか「アフリカ」とか、地域別にプレイリストを作って、気が向いたときに聞いていた。しかししばらくは、あまり長い時間、聞いていられなかった。 自分にとって、馴染みのない旋律や音色というのは、長く聴いていると不快に感じられてくる。つまり、初めてそれらのCDを聴いて、へぇ、こういう伝統音楽があるんだぁ、と感動したとしても、それを「自分の日常」のなかに取り入れるというのは、また別の次元ということになる。もし、それらに地域に特別の思い入れが事前にないのなら、しばらくの間は残念ながら"我慢"して聴き続けなくてはならない。 わたしはこのごろ、音楽でも、料理でも、良いとか悪いとか、好きだとか嫌いだとか、云わない。 ただ、うーん、これは慣れるのに時間がかかるかもしれないとか、これはすぅーっと入ってくるとか、そんな感じに表現している。 たとえば、中学生の頃、友達に「このCDいいから、聴いてみな」と云われたら、もしその友人のことが好きで信頼しているなら、もう聴く前からその音楽が"いい"と判断している、ということはよくある。なぜなら、そのくらいの年頃の人間に、"いい音楽"とか、まして"悪い音楽"とか、判断する基準がないからだ。そして、好きな異性から薦められたら、第一印象として実はそれほど"いい"とは感じられなくても、努めて、それは"いいのだ"と思おうとするだろう。 わたしにとって、高校生の頃、アメリカやイギリスのロック(当時はどっちの出身か、ほとんど気に留めていなかったが)は、驚くほど強烈に、脳内に浸透してきた。まったく不快に感じることはなかった。おそらく、その頃、毎日、映画を借りてきては視ていたのが、影響していたように思う。わたしにとっては、その音楽は、意識的に「これはカッコいい音楽なのだ」と信じようとすべき対象だったに違いない。 しかし今はこのように考えている。この世に「カッコいい音楽」とか「カッコ悪い音楽」なんてない。有るのはただ、それを「カッコいい」とか「カッコわるい」とか思おうとさせる、何かしらのきっかけ(ほとんどの場合、友人や恋人の言葉や、メディアの反復的な宣伝文句)だけだ。 PR |
 |
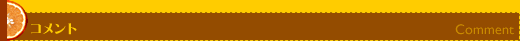 |
 |
|
|
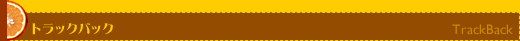 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





