 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
現代社会だと差別だけが歴然と残り、自分は奴隷らいいが何の奴隷なのかわけわからないという事態が起こっているらしいので淡々と調べてるんですが、あのさ、奴隷学ってそれ自体が歴史とか当時の風景とかと同化してるから散在してるし、理解すること自体が凄い難しいわ、こりゃあ・・・
もうこの辺なると何が何だか・・・・・ 乞胸  江戸時代に江戸市中などで、万歳や曲芸、踊りなど、さまざまな大道芸をして金銭を乞うた者。乞食(物貰い)の一種であり、元侍や町人、あるいは身元が不明な者が乞胸となった。 『乞胸頭家伝』には、以下の12の芸種が挙げられている。 綾取り - 竹に房をつけ、これを投げて取る芸。 猿若 - 顔を赤く染めて芝居をする芸。一人狂言。 江戸万歳 - 三河万歳の真似をする芸。二人で行なう。 辻放下 - 玉かくし、あるいは手玉を使う芸。 操り - 人形を操って見せる芸。 浄瑠璃 - 義太夫節や豊後節などの節をつけて物語などを語る芸。 説教 - 昔物語に節をつけて語る芸。 物真似 - 歌舞伎の口上や鳥獣の鳴声をまねる芸。 仕形能 - 能の真似をする芸。 物読み - 古戦物語の本などを読む芸。 講釈 - 太平記あるいは古物語を語り、講釈する芸。 辻勧進 - 芸のできない者や子どもらが、往来に座って金銭を乞うこと。 老人と障害者以外は一定額の上納金を納めなければならなかった。 明治4年(1871年)の身分制の解放令で乞胸の名称は廃止された。欧米でのジャポニスムの影響で、乞胸たちの芸も海外で好評を得、開国後の明治から大正にかけて芸人たちの渡航が一時盛んになったものの、国内にあってはハレの場から追放されていき、彼らが育んできた日本の伝統的な大道芸は次第にその姿を消していった。 驚愕の免許制奴隷?! 身分は町人だったらしいが、管轄が長吏というわけのわからなさ。 この時々日本は中世なのに税法がしっかりしており、公務員的な福祉と奴隷制が平行線で続いてるのでこの辺が理解しがたい感じかなあ・・・ PR |
 |
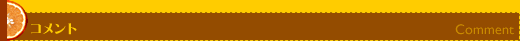 |
 |
|
|
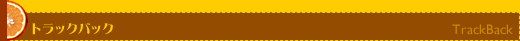 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





