 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
私のイメージはこうでした。
 いや、ドーラさんはヤクザですがイメージ的には大体こんな感じでした。 でも実際はこっちでした。 かわた  日本の近世における奴隷の別称である。 近世前期では一般的に使われていた。「かわた」の初見は永享2年(1430年)11月11日付けの土佐国香美郡の「下人売券」とされる。同文章では端裏書に「かわた四郎」と記されているが、同人が下人を買い受けたということ以外は一切不明である。その100年ほど後の大永6年(1526年)6月12日付今川氏親朱印状に「かわた彦八」の記載が見え、これによると「かわた」は「皮のやく(役)」に関係する皮革業者であった事がわかる。2年後享禄元年(1528年)10月18日付「今川氏親後室寿桂尼朱印状」によれば「かわた彦八」は急用の時には領国内の皮革を調達すべきであると命ぜられていた。 天文18年(1549年)8月24日には同じく今川氏によって「皮作商売」は八郎右衛門と彦太郎両人の独占とされ、永禄2年(1559年)8月8日には次年度分の皮革として滑皮25枚、熏皮25枚の調達を命ぜられた。 北条氏の領国・伊豆国でも天文7年(1538年)3月9日、「かわた」21名が「御用之かわ」の上納を命ぜられると共に、他人の被官になったりすることを禁じられ、弘治4年(1558年)2月27日には生皮をふすべる様命ぜられた。 これら戦国時代のかわたは、当時賎職視されつつあった皮革業に従事していたが、まだ賎民身分としてははっきりしていなかった。 かわたが本村百姓と混住している事例がみられるとしても、豊臣政権の下かわたが身分として規定されはじめていたといえる、尚、太閤検地帳の名請人の肩書きとして「かわた」と記載されているということは当時のかわたが一定の土地を持ち農業に従事していたことの証拠である。他の一般百姓と比較すれば平均持高が若干少ないという傾向はあるが、中には20石前後という高い持高のかわたも認められる。その後かわたは近世を通じて農業と深いかかわりを持ち続け、決して皮革業だけで生活していたのではなく、種々の社会階層の人々も含まれていたのである。 身分がハッキリして無いも何も、普通に奴隷売買じゃないかという突っ込み所が凄いが、元々喰いつめた人達とかが始めたりした職種のようである。 多分屠殺とかは動物なのに人間関係の方に入り、毛皮業が動物関係に入った。そんな感じ? PR |
 |
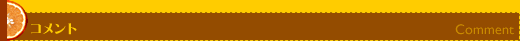 |
 |
|
|
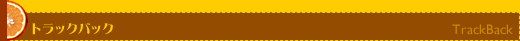 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





