 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
奥州藤原氏マジで南北朝より南北朝だった(ややこしい)
しかも滅ぼしたの源頼朝。 以下、ウィキぺ転載。 奥州藤原氏(おうしゅうふじわらし)は、前九年の役・後三年の役の後の寛治元年(1087年)から源頼朝に滅ぼされる文治5年(1189年)までの間、陸奥(後の陸中国)平泉を中心に出羽を含む東北地方一帯に勢力を張った豪族。天慶の乱を鎮めた藤原秀郷の子孫を称した。 なお奥州藤原氏が実際に藤原氏の係累であるかについては長年疑問符がつけられていたが、近年の研究では藤原経清について永承2年(1047年)の五位以上の藤原氏交名を記した「造興福寺記」に名前が見えており、同時期に陸奥国在住で後に権守となった藤原説貞と同格に扱われていることから実際に藤原氏の一族であったかはともかく、少なくとも当時の藤原摂関家から一族の係累に連なる者と認められていたことは確認されている(興福寺は摂関家の氏寺である)。また確たる史料はないものの亘理郡の有力者で五位に叙せられ、陸奥の在庁官人として権守候補であった可能性は高いと見られている。[1] また、埴原和郎は、藤原氏三代の遺体を計測したデータを分析し、奥州藤原氏は東北人ではなく京都人と位置付けている(再考・奥州藤原氏四代の遺体 )。 東北地方は弥生時代以降も続縄文文化や擦文文化に属する人々が住むなど、関東以南とは異なる歴史を辿った。中央政権の支配も関東以南ほど強くは及んでいなかったが律令制の時代には陸奥国と出羽国が置かれ、俘囚と呼ばれた蝦夷(えぞ)系の人々と関東以南から移住して来た人々が入り混じって生活していた。 11世紀半ば、陸奥国には安倍氏、出羽国には清原氏という強力な豪族が存在していた。安倍氏、清原氏はいずれも俘囚の流れを汲む、言わば東北地方の先住民系の豪族であった。このうち安倍氏が陸奥国の国司と争いになり、これに河内源氏の源頼義が介入して足掛け12年に渡って戦われたのが前九年の役である。前九年の役はその大半の期間において安倍氏が優勢に戦いを進めていたが、最終局面で清原氏を味方に付けた源頼義が安倍氏を滅ぼして終わった。 ガビーンなんという事でしょう 東北地方は元々思想犯だらけだったようです。 中部から以北は奴隷層の発想がいまいち無いのはこういう事のようです。 この辺から完全に北朝になりはじめる 清衡は、朝廷や藤原摂関家に砂金や馬などの献上品や貢物を欠かさなかった。その為、朝廷は奥州藤原氏を信頼し、彼らの事実上の奥州支配を容認した。その後、朝廷内部で源氏と平氏の間で政争が起きたために奥州にかかわっている余裕が無かったと言う事情も有ったが、それより大きいのは当時の中央政府の地方支配原理にあわせた奥州支配を進めたことと思われる。[要出典]奥州藤原氏は、中央から来る国司を拒まず受け入れ、奥州第一の有力者としてそれに協力するという姿勢を最後まで崩さなかった。 そのため奥州は朝廷における政争と無縁な地帯になり、奥州藤原氏は奥州17万騎と言われた強大な武力と政治的中立を背景に源平合戦の最中も平穏の中で独自の政権と文化を確立する事になる。その政権の基盤は奥州で豊富に産出された砂金と北方貿易であり、北宋や沿海州などとも独自の交易を行っていた様である。マルコ・ポーロの東方見聞録に登場する黄金の国ジパングのイメージは、奥州藤原氏(後に安東氏)による十三湊大陸貿易によってもたらされたと考える研究者もいる。 秀衡は平治の乱で敗れた源義朝の子・源義経を匿い文治元年(1185年)、源頼朝に追われた義経は秀衡に再び匿われた。 秀衡は頼朝からの引渡要求を拒んできたが秀衡の死後、息子の藤原泰衡は頼朝の要求を拒みきれず文治5年(1189年)閏4月義経を自殺に追い込み、義経の首を頼朝に引き渡す事で頼朝との和平を模索した。 しかし、関東の後背に独自の政権があることを恐れた源頼朝は同年7月、義経を長らくかくまっていた事を罪として奥州に出兵。贄柵(秋田県大館市)において家臣の造反により藤原泰衡は殺され、奥州藤原氏は滅んだ。 平家滅亡により源氏の勢力が強くなった事、奥州に深く関わっていた義経が頼朝と対立した事などにより中立を維持できなくなった事が滅亡の原因となった。 なんとなく統一したい理由に義経が利用された気がするので 特に首を差し出す必要性は無かったのかも(そもそも頼朝は元々制圧する言い訳がほしかっただけである)まあ、首も偽物説あるからわからんけど。 ちなみにオチはこんなかんじ。 清衡の四男・藤原清綱(亘理権十郎)は当初亘理郡中嶋舘に居城し以後平泉へ移りその子の代には紫波郡日詰の樋爪(比爪)館に居を構え樋爪氏を名乗り樋爪俊衡と称している。奥州合戦では平泉陥落後、樋爪氏は居館に火を放ち地下に潜伏したが、当主・俊衡らは陣ヶ岡の頼朝の陣に出頭し降伏した。頼朝の尋問に対し法華経を一心に唱え一言も発せず命を差し出したので、老齢のことでもありその態度を是とした頼朝は樋爪氏の所領を安堵した。しかし、その後歴史の表舞台から消えた。子や弟も相模国他へ配流された。経清(亘理権大夫)以来代々の所領地曰理郷(亘理郡)も清綱(亘理権十郎)の没落とともに頼朝の幕僚・千葉胤盛の支配する所となった。 清綱の息女の乙和子姫は、信夫荘司佐藤基治に嫁し佐藤継信・佐藤忠信兄弟(義経の臣)の母親として信夫郡大鳥城(福島市飯坂温泉付近・現在舘の山公園)に居城した。全国佐藤姓のみなもとのひとつとなった。 佐藤さんオチでした。 PR |
 |
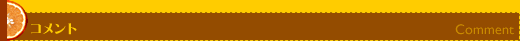 |
 |
|
|
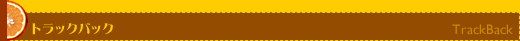 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





