 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
みんなぜんぜん無関係の
別に赤毛のマッハとか信仰してるマッハ厨でもないのに相変わらず影響ありすぎである。 天才とか不便であるな・・・ 私は天才というより秀才を目指したいのですが、どうもマジで私みたいな書き方してる奴物凄い少数派であるらしい。えーみんなテーマから描かないのか・・・・・・・そりゃ不便だな・・ 天才は基本原稿めり込みの書き方しか出来ないのでそれ以外うんこだからなあ・・ 頭使わないから基本頭悪いよ・・・ラノベだと中卒先生が有名。めり込みすぎてあとがきがオカルト狂いしててやばい。 ちなみにみんな大好き、ワルキューレさんはれっきとしたドイツ人です♪ 成田のマッハ信仰はどうなの?というと ええと、たぶん信仰してても、宗教違うし、ケルト系キリシタンか、ネオケルトにでも改宗しないと根本的なご利益を受けるとかはなさそうである。首なしライダー自体は都市伝説の妖怪だしなあ・・・日本のはろくろ首の派生ぽいけど・・ 成田、ろくろ首に取り付かれてるのか・・ていうかろくろ首ってなんだよ・・ますますわからん・・・・・ ドイツ娘のワルキューレと間違えるなふじこ!!とかいわれそうである。マッハは大体美人に描かれてることが多いね。洋画。 追記>> ありました!!抜け首という妖怪だそうです!! 以下うぃきぺ!! 首が抜けるろくろ首(抜け首) こちらの首が抜けるものの方が、ろくろ首の原型とされている[6]。このタイプのろくろ首は、夜間に人間などを襲い、血を吸うなどの悪さをするとされる。首が抜ける系統のろくろ首は、寝ている(首だけが飛び回っている)ときに、本体を移動すると元に戻らなくなることが弱点との説もある[7]。古典における典型的なろくろ首の話は、夜中に首が抜け出た場面を他の誰かに目撃されるものである[7]。 『曾呂利物語』より「女の妄念迷ひ歩く事」[8] 『諸国百物語』より「ゑちぜんの国府中ろくろ首の事」[6] 抜け首は魂が肉体から抜けたもの(離魂病)とする説もあり、『曾呂利物語』では「女の妄念迷ひ歩く事」と題し、女の魂が睡眠中に身体から抜け出たものと解釈している。同書によれば、ある男が、鶏や女の首に姿を変えている抜け首に出遭い、刀を抜いて追いかけたところ、その抜け首は家へ逃げ込み、家の中からは「恐い夢を見た。刀を持った男に追われて、家まで逃げ切って目が覚めた」と声がしたという[8](画像参照)。 『曾呂利物語』からの引き写しが多いと見られている怪談集『諸国百物語』でも「ゑちぜんの国府中ろくろ首の事」と題し、女の魂が体から抜け出た抜け首を男が家まで追いかけたという話があり(画像参照)、この女は罪業を恥じて夫に暇を乞い、髪をおろして往生を遂げたという[6]。 橘春暉による江戸時代の随筆『北窻瑣談』でもやはり、魂が体から抜け出る病気と解釈している。寛政元年に越前国(現・福井県)のある家に務めている下女が、眠っている間に枕元に首だけが枕元を転がって動いていた話を挙げ、実際に首だけが胴を離れるわけはなく、魂が体を離れて首の形を形作っていると説明している[9]。 妖怪譚の解説書の性格を備える怪談本『古今百物語評判』では「絶岸和尚肥後にて轆轤首を見給ふ事」と題し、肥後国(現・熊本県)の宿の女房の首が抜けて宙を舞い、次の日に元に戻った女の首の周りに筋があったという話を取り上げ、同書の著者である山岡元隣は、中国の書物に記されたいくつかの例をあげて「こうしたことは昔から南蛮ではよく見られたことで天地の造化には限りなく、くらげに目がないなど一通りの常識では計り難く、都では聞かぬことであり、すべて怪しいことは遠国にあることである」と解説している[10]。また香川県大川郡長尾町多和村(現・さぬき市)にも同書と同様、首に輪のような痣のある女性はろくろ首だという伝承がある[4]。随筆『中陵漫録』にも、吉野山の奥地にある「轆轤首村」の住人は皆ろくろ首であり、子供の頃から首巻きを付けており、首巻きを取り去ると首の周りに筋があると記述されている[11]。 松浦静山による随筆『甲子夜話』続編によれば、常陸国である女性が難病に冒され、夫が行商人から「白犬の肝が特効薬になる」と聞いて、飼い犬を殺して肝を服用させると、妻は元気になったが、後に生まれた女児はろくろ首となり、あるときに首が抜け出て宙を舞っていたところ、どこからか白い犬が現れ、首は噛み殺されて死んでしまったという[12]。 これらのように、ろくろ首・抜け首は基本的に女性であることが多いが、江戸時代の随筆『蕉斎筆記』には男の抜け首の話がある。ある寺の住職が夜寝ていると、胸の辺りに人の頭がやって来たので、それを手にして投げつけると、どこかへ行ってしまった。翌朝、寺の下男が暇を乞うたので、訳を聞くと「昨晩、首が参りませんでしたか」と言う。来たと答えると「私には抜け首の病気があるのです。これ以上は奉公に差し支えます」と、故郷の下総国へ帰って行った。下総国にはこの抜け首の病気が多かったとされる[13]。 根岸鎮衛による随筆『耳嚢』では、ろくろ首の噂のたてられている女性が結婚したが、結局は噂は噂に過ぎず、後に仲睦まじい夫婦生活を送ったという話がある。本当のろくろ首ではなかったというこの話は例外的なもので、ほとんどのろくろ首の話は上記のように、正体を見られることで不幸な結果を迎えている[7]。 江戸時代の百科事典『和漢三才図会』では後述の中国のものと同様に「飛頭蛮」の表記をあて、耳を翼のように使って空を飛び、虫を食べるものとしているが、中国や日本における飛頭蛮は単なる異人に過ぎないとも述べている[14]。 小泉八雲の作品『ろくろ首』にも、この抜け首が登場する。もとは都人(みやこびと)で今は深山で木こりをしている一族、と見せかけて旅人を食い殺す、という設定で描かれている。 成田すごいのにとりつかれてるな・・・正体知ったら食い殺されるて・・・ PR |
 |
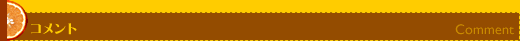 |
 |
|
|
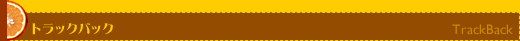 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





